![]()
![]()
 |
| (六厩の紅葉) |
| 10月21日 六厩川 |
このあたりの紅葉は、ようやく始まったばかり。でも、所々には赤やら黄色く染まった木々を見かけます。掲載の写真はお恥ずかしい限りの駄作ですが、とりあえず、これくらいに染まった木もあるということ。まだまだ緑の方が多いです。 今年は昨年に比べると、紅葉の進み具合は遅いです。 さてクマ棚ですが、まず六厩川の女滝下流の別荘地あたりに車をとめて散策するも、それは発見出来なかった。それでそのまんま大蓑林道を歩いてみたけど、やはり発見出来なかった。今年は山の実りが良いみたいだから、クマはここまで降りてくる必要が無いのかも知れん。 もっとも、まだ緑が多くて見通しが利かず、せいぜい20m先くらいのクマ棚しか確認できないので、その先にクマが潜んでおる可能性もある。 ただ、昨年のクマ棚の残骸の残る木々は葉っぱの付き具合も悪く、そしてドングリも少なかった。まあ、あれだけボキボキと枝を折られたんでは、ドングリの木もたまったもんではない。そりゃあ実りも少なくなりますわな。クマもそのことを承知で、今年は別の地域でドングリを食っとるのでしょう。・・・・が、私の結論。 1時間半ばかり林道を歩いただけなのに、腰が痛くなった。 その後、女滝の上流を歩いてみたら、1本の木にクマ棚を発見。それは青々としてて、その幹にはしっかりと爪痕を確認できた。多分、出来立てホヤホヤ。 ただ、それはあまりにも貧相なクマ棚で、その周りをみてもクマ棚はない。多分きっと、たまたまここを通りかかったクマが、ちょいと小腹が空いたので仕方なく木によじ登って、おやつ感覚でドングリをかじった程度だと思った。 ところで「クママップ」というのをご存知でしょうか? これは岐阜県限定ですが、クマの出没状況を地図に表したものです。 それによると私の行動範囲内では、今年の7〜9月にかけて、鷲見・古道・鹿倉・八幡町初納あたりにも出てます。私はそんな事も知らんと釣りしてました。 ただ、石徹白の報告は無い。この地域はそんなこと日常茶飯事だから、誰も報告しない。 人口密集地か、普段クマの出ない地域の出没状況が中心でしょう。 釣り人にとっては意味の無い情報かとは思いますが、私としては、見ていて楽しかったりします。 アドレスはこちらです。 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11264/sizen/kuma/index.htm |
![]()
 |
| (オフシーズンの手慰み) |
| 11月11日 竿作り |
| この週末の天気予報はあまり芳しくなかったので、竿作りに励みました。 実は10月に入ってから、チマチマとやっておったのですが、曲がり直しから荒削りまで終わってて、後の火入れ〜仕上げ削り〜接着のタイミングを計っておったのです。火入れをしたからには、少しでも水分を含ませたくないから、速攻で接着までもっていかねばならないのです。 それで金曜日の夜に火入れして、土日に仕上げ削りと接着作業にとりかかりました。 土曜日は外出の予定は全く無いから、朝からビール缶を開けて、のんびりと竹を削ります。なんか朝っぱらからビール飲むのって、すごい贅沢なような気がして、とても心地よろしい。それに、何かの作業をしながらのビールは、とても美味しいと思うのだ。たとえば、料理しながらのビール。時々味見しながら、それをつまみにビールを頂く。川でケーチャン作りながら、やっぱりビール飲みますよね。その感覚です。 まあ、そんな感じでの竿作りなんで、当然作業効率は落ちます。真剣にやれば1日で完成する作業ですが、日曜日にも竿作り。3時くらいに仕上げ削りは完了して、接着作業に入る。今回は2本の竿を作っていて、バット2本を接着してティップの1本目を接着してるところへ船長がやってきました。 いやいや、どーもどーも、と言いながら招き入れるも、本当のところ、私はあせってた。接着作業の時間は早いにこしたことはない。でも慌てたところを見せたくないから、その1本目のティップをゆっくりと接着してからコーヒーを馳走する。あくまで鷹揚に。 暫し会話の後(白山林道の入り口には、クマ棚が一杯あるらしい)、私はおもむろに最後のティップの接着にとりかかる。船長がシゲシゲと見とるので、ちょっと緊張する。 仕上げ削りを終わった6辺の竹片の裏側に接着剤をたっぷり塗って仮止め。それをバインダーにセットして麻糸でクルクルと締めていきます。途中で2回テンション圧を変更。そして最後の一番細い部分で折り返す訳ですが、そこで急にテンションが重くなった、と思ったら、ポキリと折れた。先っぽ2cmの部分。過去30本も作っとるのに、こんんな事は始めて。これは船長の目のプレッシャーのせいか・・・。 いや、以前見た記事では、「本物の職人は、人に見られてても平素の作業が出来る」人の事を言うらしい。私は修行不足なのだ。(まあ、いつも先っぽの2cmは切り落としてるので、竿の調子には影響ないはずです) さて、今回作る竿の1本は、オリジナルテーパーの7’3”#4。これは前回作ったのがどうも変な調子で、持ち重りがするかというか、先っぽが硬すぎる感じがして使用に耐えなかった。それでティップ部を少しだけ細くした。まあ、実際にラインを通して振ってみなければ結果はわかりません。 もう1本はレナード38H(7’0”#4)のレプリカ。 そもそも私は、その38Hのテーパーで竿作りを始めたんですが、当初は竹削りがヘタクソでとても正三角柱には削れなくって、イビツな三角柱を6本まとめても、べろんべろんな調子の竿しか出来なかった。で、そのベロンベロンな竿を参考に次の竿のテーパーを決めて竿を作って、そしてまた、その竿を参考にテーパーを決めて・・・、の繰り返し。そもそも竹削りがヘタだったんで、それを参考にするのが間違っておったのですが・・・。 私の竿作りは、随分と遠回りをしてます。誰か経験者の助言があれば、ほんの数本の作製でそのコツがつかめたものを、私の場合は十数本の作成が必要となってしまいました。これから竿作りをやろうと思ってる方は、ぜひとも経験者に従うべし。 ところで、オリジナルの7’3”#4とレナード38Hのテーパーを比較すると、バット部はほぼ同じテーパーになってます。まあ、基本がレナードだから、それもうなづける。が、ティップ部はオリジナルの方が2回り細い。これは私の試行錯誤の結果そうなった。前回の試作でも太いと思ったのだから、やはりレナードとは極端に違う。 となると、今作ってるレナード38Hのレプリカは、きっと棒のような竿になると思う。そう言やあ、以前知人にアメリカ産のウン十万の竿を振らしてもらった時の印象も、棒を振ってる感覚だったな。私の技術では、そんな竿は扱えない。 7’3”#4は、多分使える竿にはなるとは思うけど、レナード38Hのレプリカは、私のキャスティング技術じゃぁ使えないと思う。 無駄な作業とは思いながも、とりあえずは参考のために作るのです。 |
![]()
 |
| 12月11日 いえそば |
| え〜、久々の更新となりますが、釣りの話でも、川の話でもありません。「いえそば」のお話です。 実は先月18日、船長と師匠とで自転車行をした折、あいにくの雨で自転車を車に積み込んだまま、カッパを着て川原でトロロ蕎麦を食っておった時のことです。 船長:「ところで、タカラトミーから手打ち蕎麦が出来るオモチャがあるけど知ってた?」 私:「知らん。でもあそこは焼き物のできるオモチャがあったな。その第2弾かな。それで、どんな事が出来るの」 船長:「たしか、そば粉と水を混ぜ合わせてくれて、あと玉は自分で捏ねんといかんけど、蕎麦きりはやってくれる」 私:「へ〜、欲しいな。いくら?」 船長:「1万ちょっとかな?」 私:「船長、買って!」 船長:「アンタが買いなさい!!」 師匠:「・・・・・・・」  師匠はまったく興味がないのね。でも私はすごく興味があったから、帰宅後にいろいろ調べた。 師匠はまったく興味がないのね。でも私はすごく興味があったから、帰宅後にいろいろ調べた。まず、そば粉と水を混ぜ合わせる作業を「水まわし」と言って、これが素人の蕎麦打ちには一番やっかいらしく「水まわし3年」なる格言まであるらしい。それをこのオモチャはいとも簡単にやってのけるんだとか。本当か・・・? あと、うどんも打てるし、たったの20分で蕎麦打ちが出来るらしい。一度に打てるのは2人前らしいが、やりようによっては4人前でも6人前でも出来るらしい。 すべての情報は、・・・らしいが前提です。 それで少し悩んだあげく、アマゾンで注文したのが3日に到着。9440円でした。 そば粉も注文したものの、到着は翌日だったので、バローへ走ってうどん粉を購入。早々にうどん打ちです。 マニュアルに従って作業を進めるも、なかなかその通りには行かなくって苦労するし、右の写真のように「いえそば」から切り出された麺も、とてもパッケージのようには行かない。(写真の左下の塊は、最初に切り出したやつ。餅のように固まってしまった)あたりはうどん粉だらけになるし・・。 でもそのイビツな麺を茹で上げたら、腰のあるプリプリな麺に仕上がって、とても美味しく頂けた。 翌日にはそば粉も届いたので、今度こそ手打ち蕎麦を作る。 が、やはりマニュアル通りにはいかない。20分で出来る、とあるが、私には小一時間かかる。それから、水洗いした麺が切れ易すかったりもする。少し要領を覚える必要がありそうだ。 でもやっぱり出来上がった蕎麦は、ほんのりとした香りと甘みがあり、とても美味しく頂いたのでした。 この1週間は、日々お蕎麦を食っております。 なお、この「いえそば」ですが、某倶楽部でも購入を検討してるらしい。 また私の姪っ子夫婦は、発売当初の10月に購入したらしい。 少なくとも私の周りでは、結構人気があるようです。 「いえそば」の詳細はこちらをどうぞ。 http://www.takaratomy.co.jp/products/iesoba/ |
![]()
 |
| (いえそばで、年越しそば) |
![]()
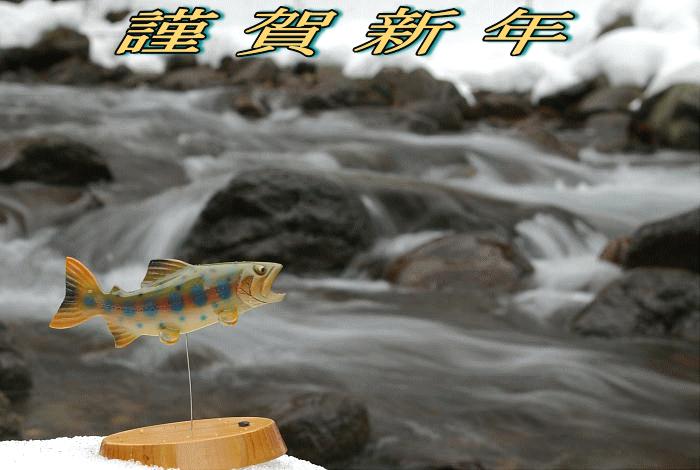 |
| 1月1日 謹賀新年 |
| 皆様、明けましておめでとうございます。 本年も相も変らぬお付き合いの程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 上の写真は、23日にK100Dの試し撮りをした時のもの。1/8秒・手持ち撮影。なかなかよろしいです。 場所は九頭竜の国道下で、この時の積雪は20cmくらい。道の横に車を止めて、長靴履いて林道をトコトコ20mばかり行った所での撮影でした。 今現在そこへ行こうとすると、1.5m以上の積雪に阻まれて、たとえカンジキを履いていたとしても、きっと遭難することでしょう。 私の1月1日は、屋根の雪下ろしからのスタートでした。 |
![]()
| 1月13日 「いえそば」実習 |
| ここ数日、私の掲示板が表示されなくなっております。サーバのディスクが壊れたらしい。それでディスク交換後もうまく動かないらしい。そもそもサーバが壊れた可能性もあるとの事で、復旧には数日かかるとのことです。 まあ無料掲示板なのでね、のんびり待ちます。 13日には師匠と船長をお招きして「いえそば」実習会を開きました。 実習会なので私は何もしません。師匠と船長に実習していただくのです。私のやったのは粉と水の計量と、最初の「のし」に入る形を作るのと、洗い物だけ。あとはビール片手に、「あーだ、こーだ」と指示する。お二方は、私の指示通りに動くので、とても気分がよろしい。 船長は一度、私の作ってる所を見てるので、おおよその要領は判ってます。それでまず、最初の「玉」をのして切っていく。簡単なことです。次に師匠もその通りにやる。もう、本当に簡単なことです。こんなの、1回見れば誰だって出来る。 そして完成した蕎麦が上の写真(この日私は1枚も写真を撮らなかったので、この写真は船長から頂いた物)。ツルリとしたのど越しで、噛むとほんのりとした甘みがある。「いえそば」は、誰が作っても同じ味になるようです。美味しいぞ。 さて、この日は小・新年会でもあるので、蕎麦の前には乾杯をする。つまみは師匠持参の「からすみ」をダイコンのスライスに挟んで食す。珍味です。片手に乗るくらいの大きさで数千円もするという品物で、当然ながら師匠も、人からの頂き物だそうです。「からすみ」は、人から頂いて食す品物です。 蕎麦の後には、船長の作ったスパイスカレーを頂く。本人曰く「郡上味噌が入ってるので、本物の”奥美濃カレー”なのだ」そうですが、味噌の味は全くしなかったのでよかったです。それより、今までに味わった事のないスパイスが入ってるのか、とても不思議な味がしました。まあ、私が本物のカレーを知らないだけだと思います。でも、とてもとても美味しゅうございましたよ。 今シーズンの釣り目標は・・・。 「今年も無事に9月30日を迎えられますように」 で、3人とも意見が一致。即決でした。 |
![]()
 |
| (ウサギが、向こうからこっちへ走り去った跡) |
| 1月27日 田茂谷 | ||||
| もうすぐ解禁ですね。私らのように日々雪を見て過ごしてると、そんな事は全く感じなくって、それは誰かが口に出して言ってくれないと実感が湧いては来ません。 昨日船長が来て「もうすぐ解禁ですな〜」と言った。 う〜ん、解禁か〜。いい響きだな〜〜。 急に渓流が恋しくなって、今日は田茂谷を散歩してきました。 積雪は4〜50cmあるものの、締まった雪の上は普通の長靴で歩ける。念のために持っていったカンジキは無用に終わってしまいました。 ウサギとタヌキ?の足跡以外は全くの無いピカピカの新雪の上を歩くのは、とても心地よろしいです。
|